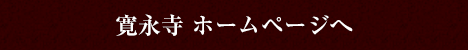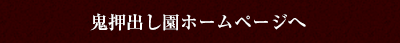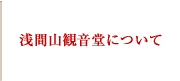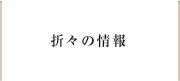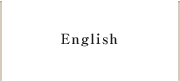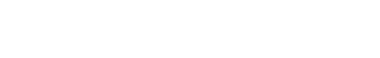|
世界三大奇勝の一つに数えられる「浅間山鬼押出し」の中央に鎮座する、東叡山寛永寺別院浅間山観音堂は、浅間山噴火罹災者への慰霊と自然への畏敬をもって、その平穏を祈願する道場です。 江戸時代の天明3(1783)年、浅間山が大噴火を起こし、多くの方が犠牲になりました。その際に最大の被害を受けたのが鎌原村だったのです。鎌原村には当時寛永寺の末寺として、浅間山明神の別当寺である延命寺という寺がありましたが、このお寺も噴火により埋没してしまいました。そのため、噴火罹災者の救済を時の寬永寺住職である「輪王寺宮(りんのうじのみや)」公延法親王が命じたと言われています。 こうしたことをご縁として、昭和33(1958)年5月に上信越高原国立公園内に位置する「鬼押出し園内」に、寛永寺より聖観世音(しょうかんぜおん)菩薩を迎え、浅間山観音堂が創建されました。以来、あらゆる自然災害罹災者の慰霊と被災地の復興を祈願し続け今日に至ります。 そして平成30(2018)年、当堂は創建60周年を迎えました。 |

|
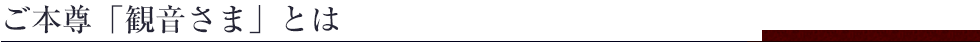
|
観音さまと呼ばれ多くの人々に信仰されている仏さま、正式には「観世音菩薩」又は「観自在菩薩」とお呼びします。世の全てを見通し、救いを求める声を聞き逃さないことからこのようにお呼びします。
観音さまを称えるお経の一節に、次のような文言があります。 「たとえばあなたに対する悪意があって 火を噴く大きな穴にあなたが落とされそうになった時に 観音さまを一心に念ずると 火を噴く穴が池となるのです」。 なんだか浅間山の火口に落とされそうになる光景が想像できてしまいますが、このお経に説かれる「火を噴く穴」は、もちろん火口を想定したものではありません。実は私たちの中にわきあがる「怒りの炎」などを指すのです。 悪いことをしないようにして良いことをしよう、というのはごく当たり前のことです。ですが、どれだけ良いことをしても、一度の「怒りの炎」で台無しになってしまうとされています。こうしたなか、観音さまのお力を頼ることで炎のような怒りが収まり、輝く水面の池のように心が静まるのです。 観音さまのお力は怒りだけでなく、むさぼりや愚かさを整えると言われております。ぜひご本尊さまにお手合わせいただきますようお願い致します。 |
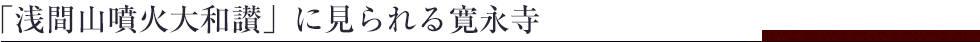

|
明治初年、滝沢対吉の原作・鎌原司郎の補正により、天明の大噴火を風化させないとの思いから、七五調の日本のことばで「浅間山噴火大和讃」が作られました。和讃の後半部分には、噴火から命からがら逃げた93人が寛永寺に供養を依頼した情景を見ることができます。それによれば、被災者の依頼に応えた高僧が多くの僧侶を引き連れ供養を行った際に、参加した被災者も皆な合掌して「南無阿弥陀仏」と唱えたところ、犠牲者が極楽に導かれ被災者の心も開かれ涙が止まった光景が読まれています。
全文をご紹介いたしますので、ぜひ声に出して唱えてみて下さい。なおこの和讃は「鎌原観音堂(かんばらかんのんどう)」で今でも唱えられ供養が続いています。
|

|
「輪王寺宮(りんのうじのみや)」は、幕末までに皇室出身で寛永寺の住職となった方の称号です。皇室出身者が住職を務める寺は「門跡寺(もんぜきじ)」と呼ばれ、京都を中心にいくつもありましたが、寛永寺を創建された天海大僧正は寛永寺を東日本で初めての門跡寺にしようと考えたのです。 残念ながら天海大僧正の生前には実現されませんでしたが、寛永寺の第3代住職に「守澄(しゅちょう)」法親王が就任したことで、その念願は達成されました。守澄法親王は、お釈迦さまを意味する「転輪聖王(てんりんじょうおう)」から取った「輪王寺宮」という称号となったこと、また「一品(いっぽん)」という極めて高い格式を持ったこと、さらに寛永寺だけでなく日光山と比叡山の山主を兼ね「三山管領宮(さんざんかんりょうのみや)」と呼ばれたことなどで、寛永寺の住職というだけにとどまらず日本の宗教界の上に立つ存在となったのです。こうしたことは明治初期の神仏分離まで続きました。 |

| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 春秋二季 | 大祈願祭 | 寛永寺別院 浅間山観音堂 |
| 7月8日 | 天明供養祭 | 寛永寺別院 浅間山観音堂 |
| 毎月18日 | ご縁日法要(本尊:聖観世音菩薩) | 寛永寺別院 浅間山観音堂 |

|
浅間山観音堂へお越しの方は |